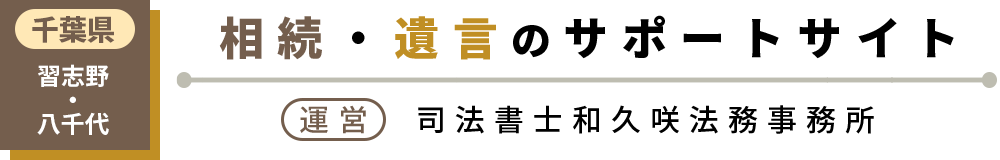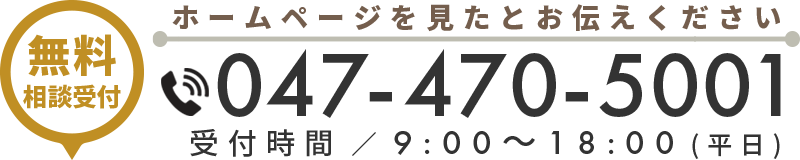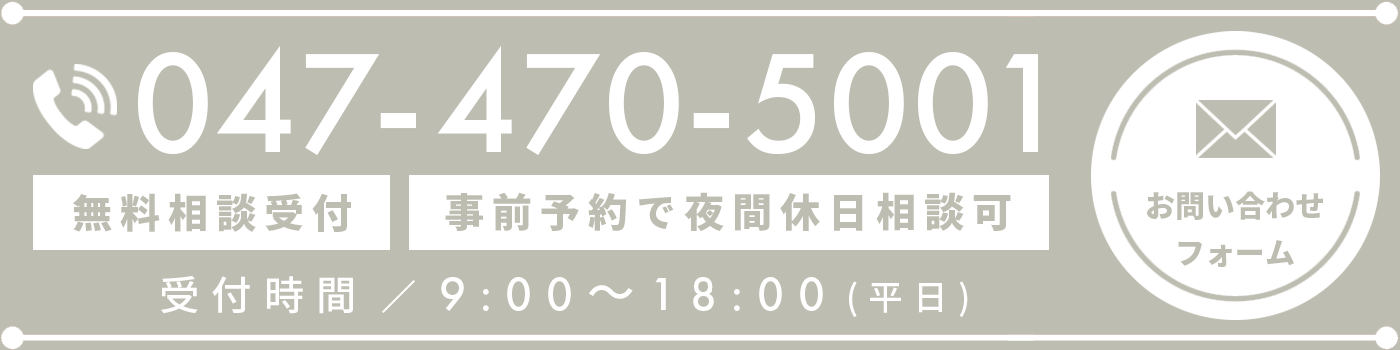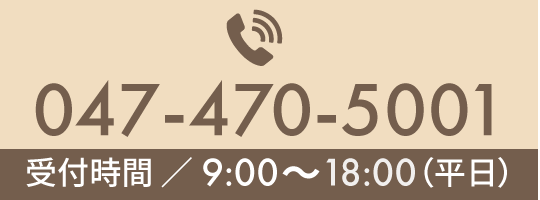このページの目次
相続手続には遺産分割協議が必要なことが多い
不動産の名義変更や預貯金の解約など相続手続では、遺産分割協議(書)が必要なことが多いです。
その遺産分割協議は、相続人の全員の同意が必要とされています。
遺産分割協議(書)とは
亡くなった方(被相続人)が遺言書を作成していなかった場合、相続の方法は次の2パターンになります。
①民法が定めた法定相続分に従って相続人全員で相続する
②相続人全員の同意により①とは異なった相続人・割合で相続する
②のパターンの相続人全員による話し合いを「遺産分割協議」と呼んでいます。
遺産分割協議は、相続人全員が納得する限り、どのような内容でも構いません。
ポイントは、【相続人全員の合意】です。
例えば、父が亡くなり、相続人が母・子二人のような場合に、相続人全員である母・子二人が話し合って(遺産分割協議をして)、自宅・預貯金など父の相続財産すべてを母が相続する、というような取り決めに合意できれば、それで構いません。
その点、相続というと「法定相続分」が気になる方もいるかもしれません。
「法定」となっているので、あたかも法が定めた割合通りに分割をしなければならないような感じにもなってしまいますが、そこは、相続人全員が合意する限り、法定相続分にとらわれる必要はありません。
ちなみに、遺産分割協議について民法では「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906条)と定められており、必ずしも法定相続分で分割しなければならないと定めているわけではありません。
また、相続人全員の話し合いを「遺産分割協議」と言いますが、民法では、その結果を必ずしも書面にすることは求められていません。
しかし、不動産の名義変更(相続登記)などでは結果を書面化した「遺産分割協議【書】」が必要とされていますし、相続登記が無い場合であっても、後日のために遺産分割協議【書】を作成することが多いと思います。
相続人が認知症だった場合
このように遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要なのですが、相続人の中に高齢で認知症の方がいる場合もあります。
認知症の方は、「この遺産はほしい」「この遺産はいらない」「相続したい」「相続したくない」などという意思表示が困難なことが多いです。
つまり、認知症の方は実質的な遺産分割協議には参加することが難しいと考えられます。
とはいえ、そのような方(認知症の方)を除外して遺産分割協議をすることも出来ません。
その場合は、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加する人を選ぶ必要があります。
その人が「成年後見人」です。
成年後見人の選任
相続人の中に意思表示が困難である認知症の方がいる場合は、成年後見人の選任を検討する必要があります。
成年後見人は、認知症の方の代理人になる人ですが、親族などが勝手に決めることはできません。
家庭裁判所の手続によって選任してもらう必要があります。
家庭裁判所に、申立書や医師の診断書など必要書類をそろえて申立をします。
申立から成年後見人が決まるまでに3ヶ月程度かかります。(ケースによって期間は異なります。)
成年後見人についての留意点は次のとおりです。
・申し立てた親族が望む人が成年後見人に選任されるとは限らない
→成年後見人は家庭裁判所が決める
・一度成年後見人が選任されると、基本的には一生涯、成年後見人が付いたままになる。
→遺産分割協議のためだけに選任されるわけではない。
・申立後に、申立を取り下げ(中止する)ことはできない。
・成年後見人に専門職(司法書士・弁護士等)が選任された場合は、家庭裁判所が決めた報酬を支払う必要がある、など
このように成年後見人を選任してもらい、認知症の方に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することとなります。
ちなみに、成年後見人が選任された認知症などの方を、成年被後見人といいます。
遺産分割協議と成年後見人
無事、成年後見人が選任されればいよいよ遺産分割協議なのですが、ここでも留意点があります。
それは、遺産分割協議の内容として、原則、成年被後見人の取得割合を法定相続分以上にする必要があるという点です。
例えば、父が亡くなり、その相続人として母・長男・長女の3人が相続人であったとします。
父の相続財産は、主に自宅の土地・建物であり、預貯金はごくわずかだったとします。
母は認知症により遺産分割についての意思表示をすることができません。
長男・長女としては、すべての財産を長男が相続した方が良いのではないかと考えています。
この事例の場合、仮に母が元気であれば相続人全員の合意によって、すべての財産を長男が相続することもできます。
しかし、母に成年後見人が選任された場合は、母の相続分として法定相続分以上の財産を確保する必要があります。
具体的には、母の法定相続分は2分の1なので、父の財産の2分の1以上を確保する必要があります。
そのため、この事例の場合、「長男がすべての財産を相続する」という内容の遺産分割協議は、基本的には認められないと考えられます。

千葉県習志野市東習志野にある「司法書士和久咲法務事務所」は、相続手続や遺言書作成など、相続や終活に関するご相談を専門に承っております。代表司法書士の景山悟は、平成29年の開業以来、200件以上の相続手続や20名以上の成年後見人業務に携わり、地域の皆様のお力になれるよう日々努めております。初回相談は無料ですので、相続や遺言、成年後見などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。